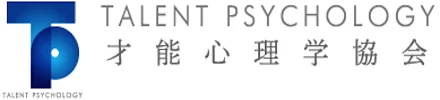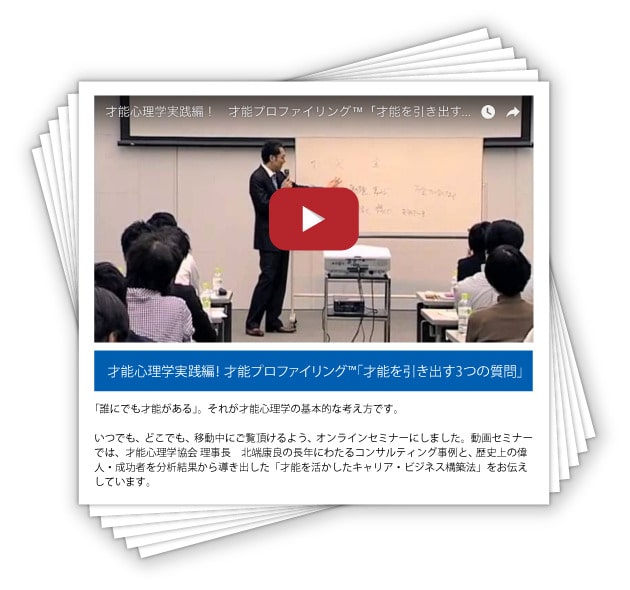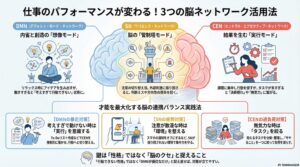仕事でも研究でも、私たちはつい「数字」「成果」「性能」など、測定できるものばかりを追いがちです。営業であれば契約数、マーケティングならCV率、研究なら性能データ。しかし、それだけを目標にしてしまうと、発想が小さく閉じてしまうことがあります。
発想が小さければ、あなたの強みや才能を大きく活かすことはできません。
では、どうすれば発想の枠を広げることができるのでしょうか?
この記事では、“思考の枠”を越えるヒントを、ノーベル化学賞を受賞された京都大学特別教授・北川進博士のエピソードから解説します。
そのアイデアではコンセプトが小さい──北川博士の助言
ある研究員が、「新しい多孔性材料の吸着性能を測定したい」と提案しました。性能を定量化して評価するのは、科学の基本です。ところが北川博士は、その提案に対してこう言いました。
「単なる性能評価だけではコンセプトとしては小さい。性能測定という枠だけでなく、環境技術やエネルギー・社会全体の枠組みまで視野を広げてはどうか?」
さらに博士は続けます。
「たとえば『分子吸着』という現象を、“新しい反応場の創出”や“持続可能な物質転換、省エネルギー社会の基盤構築”として考えてみたらどうか?」
つまり、「何を測るか」から「それが社会にどんな意味をもつか」へ視点を広げることを促したのです。
“位置づけ”を変えると、研究のスケールが変わる
北川博士の助言は、『分子吸着』という現象そのものを変えるのではなく、その位置づけ(文脈)を変えることでした。
若手研究員が考えていたのは、「分子がどれだけ吸着するか」というミクロな性能評価。 一方、博士は「その現象が社会的課題にどう貢献するか」というマクロな文脈を提示しました。
すると研究は、単なるデータ収集ではなく、「持続可能な社会の基盤技術をつくる」というビジョンへと昇華します。
実際、北川研究室からはこのような視点転換をきっかけに、 エネルギー貯蔵やCO₂回収技術に応用される革新的な成果が次々と生まれました。
ビジネスにも通じる「発想のスケールアップ」
このエピソードは、科学者に限らず、すべてのビジネスパーソンに通じる発想法です。
私たちも日常業務で、
- 営業 → 契約数を伸ばす
- 人事 → 離職率を下げる
- 経営企画 → KPIを達成する
といった「性能測定型の思考」に偏りがちです。
もちろんこれらは大切ですが、北川博士の言葉を借りれば、「測定の先にある意義を再定義せよ」ということになります。
「測定」→「意義」→「ビジョン」への3ステップ
北川博士の思考法は、ビジネスで次のように応用できます。
| 段階 | 自問すべき問い | 発想のスケール |
| ① 測定 | 何をどのように評価するか? | 小 |
| ② 意義 | それはどんな価値を生み出すか? | 中 |
| ③ ビジョン | それが社会全体にどうつながるか? | 大 |
たとえば、人事で「離職率を下げたい」と考えた場合、
- 測定の段階:データ分析で離職の原因を探る
- 意義の段階:社員が安心して働ける職場環境をつくる方法を考える
- ビジョンの段階:社員が長期的に成長できる社会を構築する方法を考える
発想のスケールを一段階上げると、課題とコンセプトのスケールも一段上がります。
発想を大きくするとは、視野を広くすること
北川博士の思考法は、「夢を大きく持て」という精神論ではありません。目の前の事実やデータを、より広い文脈の中で再定義することです。
博士が科学の世界で示したように、
- 「性能測定」という枠の中に留まるか
- 「社会全体の構造を見通す」まで広げるか
で、成果のスケールはまったく変わります。
あなたの仕事にも、“性能測定型”の思考が潜んでいませんか?
「数字を出す」から「価値を生み出す」へ。
「性能を測る」から「未来をつくる」へ。
北川博士の問いかけは、こう促しているのかもしれません。
「あなたの発想は、まだ“小さな測定”で止まっていないか?」
まとめ:小さな発想を“大きな物語”に変えよう
北川進博士のエピソードから、発想のスケールを拡大する思考法を学びました。
鍵となるのは、目の前の現象を「社会的文脈」で捉え直すという視点転換です。
- 「測定」の段階で止まらず、
- 「意義」を定義し、
- 「ビジョン」へと昇華させる
この3ステップを踏むことで、単なる小さなデータや結果も、未来の価値や社会的意義を生み出す物語へと変わります。
最後に、あなたへの問いかけです。
あなたの日常業務における「契約数」や「KPI」といった測定値は、その先にどんな社会的な価値を生み出すことができるでしょうか?
「性能を測る」という思考の枠の中に留まるのか、それとも「持続可能な社会の基盤」や「社員が成長できる未来」という構造を見通すまで視野を広げるのか。その選択が、あなたの成果のスケールを決定します。
北川博士のエピソードは、科学とビジネスの境界を越え、私たちの発想を拡張させる原点を教えてくれています。
重要なのは、どんなに小さな現象やデータを見ても、その先に広がる大きな可能性を想像し、積極的に再定義するクセを習慣化すること。
発想のスケールを変えることで、日々の仕事や研究も、世界に貢献する新しい価値を生む「大きな物語」につながります。
さあ、今日からあなたの思考を一段階上げ、あなたの強みや才能の価値を最大化していきましょう。
関連記事